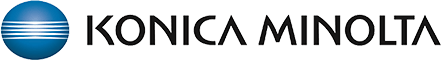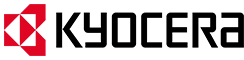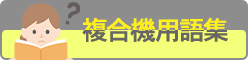オフィスに欠かせない複合機ですが、「そろそろ寿命なのでは?」「買い替えのタイミングはいつ?」と悩む方は少なくありません。
実際、複合機の買い替え時期には、税務上の「法定耐用年数(5年)」と、実際の使用に基づく物理的な寿命(5~10年)という2つの基準があります。
これを混同すると、会計処理やコスト計画に誤解が生じたり、買い替えの判断を誤ったりするリスクもあります。
本記事では、複合機の耐用年数に関する正しい知識を整理し、減価償却や会計処理の基本、買い替えのサイン、寿命を延ばす工夫、リース契約との関係まで詳しく解説します。
読み終える頃には、自社に最適な複合機の運用や更新判断ができるようになります。
目次
複合機の法定耐用年数と物理的寿命
複合機を導入する際に多くの企業が気になるのが「どのくらい使えるのか?」という寿命の問題です。寿命を判断する指標には、会計処理に基づく「法定耐用年数」と、実際の使用環境や印刷頻度によって左右される「物理的な寿命」があります。
本章では、この2つの考え方を整理しながら、複合機の買い替え判断に役立つ基礎知識を解説します。
複合機の法定耐用年数は5年
複合機の耐用年数について調べると、まず出てくるのが「法定耐用年数」という考え方です。
これは税務処理における減価償却の基準年数を意味しており、国税庁が資産区分ごとに定めています。
複合機・コピー機は「工具器具備品」に分類され、法定耐用年数は5年とされています。つまり、複合機を購入した場合は、その取得金額を5年間に分けて経費として計上していく必要がある、というのが会計上のルールです。
例えば、150万円の複合機を購入した場合には、毎年30万円ずつを減価償却費として計上する形になります。
ここで注意したいのは、この「5年」が機械として必ず使えなくなる期限ではないという点です。あくまでも「会計上の基準」としての年数に過ぎません。
複合機の実際の耐用年数は5~10年
「物理的な寿命(実際に使える年数)」は法定耐用年数とは異なります。複合機は精密機械であり、印刷枚数・設置環境・定期メンテナンスの有無といった条件によって寿命が大きく変わります。
毎月数千枚以上の大量印刷を行うオフィスでは、部品の摩耗や紙詰まりの頻発により寿命が短くなる傾向があります。一方で、利用頻度が少なく、純正トナーや推奨用紙を使用し、定期的に点検を受けている場合は、10年近く使い続けられるケースもあります。
つまり、「法定耐用年数=寿命」ではなく、あくまで会計上の目安であると理解することが重要です。実際には、5年を過ぎても問題なく稼働する複合機は多く、逆にハードな使い方をしている場合は、5年を待たずに不具合が出始めることもあります。
こうした違いを押さえることで、「税務上の耐用年数」と「実際の使用可能期間」を切り分け、買い替えやリース更新の判断に役立てることができます。
複合機の減価償却と会計処理
複合機は数十万~数百万円する高額な設備投資となるため、購入時には会計処理の方法を理解しておくことが欠かせません。特に「減価償却」という考え方は、税務処理や資金計画に直結します。
また、購入とリースでは処理方法が異なり、企業のキャッシュフローにも大きな影響を与えます。本章では、複合機の減価償却の基本から中古機の注意点、さらにリース契約との違いまで整理して解説します。
複合機の減価償却とは?基本と種類
複合機はオフィスに導入した時点で資産として計上され、法定耐用年数5年を基準に減価償却を行います。減価償却とは、資産の購入費用を一度に経費にせず、使用年数に応じて分割して費用計上する会計処理のことです。
複合機に適用される主な減価償却方法は次の2つです。
| 減価償却方法 | 計算方法 | 特徴 |
| 定額法 | 取得価額 × 償却率(複合機は耐用年数5年で0.2)例:100万円 × 0.2 = 20万円/年 | 毎年同じ金額を均等に償却。 資金計画が立てやすく、個人事業主に多い |
| 定率法 | 初年度:取得価額 × 償却率(複合機は5年で0.4)例:100万円 × 0.4 = 40万円 2年目以降:未償却残高 × 償却率 | 初年度の負担が大きく、年々減少していく。法人における原則 |
定率法のイメージ(100万円の複合機を購入した場合)
- 1年目:100万円 × 0.4 = 40万円
- 2年目:60万円 × 0.4 = 24万円
- 3年目:36万円 × 0.4 = 14.4万円
※いずれの方法でも最後に「備忘価額」として1円を残すルールがあります。
法人の場合は原則として定率法が使われますが、届出をすれば定額法に変更できます。個人事業主は定額法と定率法のどちらも選べるため、安定した資金計画を立てたい人は定額法を選ぶケースが多いです。減価償却は節税効果にもつながるので、自社の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
複合機購入時の会計処理と中古機の注意点
複合機を購入した場合は、その金額を資産として計上し、減価償却によって5年で費用化します。ただし、中古複合機の場合はルールが変わります。
- 新品価格の50%以上で購入した中古機 → 新品同様に「耐用年数5年」で計算
- 新品価格の50%未満で購入した中古機 → 下記の式で「使用可能年数」を見積もる必要あり
計算式の例:
- 法定耐用年数を超えている場合 → 法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数を超えていない場合 → 法定耐用年数 - 経過年数 +(経過年数 × 20%)
中古機を導入する際は、取得金額や経過年数によって耐用年数が変動するため、会計処理が複雑になりやすい点に注意が必要です。
リース契約との違いと会計処理のメリット
複合機をリース契約で導入した場合は、購入時のように減価償却を行う必要はありません。リース料金は、毎月の経費にそのまま計上できます。
- 購入の場合:減価償却が必要(法定耐用年数5年を基準に計算)
- リースの場合:毎月のリース料を経費計上するだけでOK
つまり、購入は資産計上して管理する手間が増える一方で、リースは会計処理がシンプルです。特に中小企業や個人事業主にとっては、キャッシュフローを安定させやすいメリットがあります。
複合機の買い替え時期のサイン

複合機は高額な設備であり、できる限り長く使いたいと考える方は多いでしょう。しかし、耐用年数を過ぎると修理や維持にコストがかかり、業務効率を下げてしまう可能性があります。
ここでは「買い替えを検討すべきサイン」を具体的に紹介します。
印刷品質の劣化
複合機を長期間使っていると、印刷結果ににじみやかすれが目立つようになります。トナーやドラムの交換で一時的に改善できる場合もありますが、頻繁に同じ症状が出るようであれば、本体の劣化が進んでいる可能性が高いです。
特に、文字の輪郭がぼやけたり、色の再現性が落ちたりする場合は買い替えを検討すべきサインです。
紙詰まりの頻発
紙詰まりが増えるのも重要なサインです。正しく用紙をセットしても給紙されない、複数枚が同時に送り込まれるといった現象が頻繁に発生する場合、内部の給紙ローラーや搬送部品が摩耗している可能性があります。
簡単な清掃やローラーの交換で解決できることもありますが、トラブルが繰り返されるようであれば、本体そのものの寿命が近づいていると考えられます。紙詰まりは作業の中断を招き、業務全体の効率を下げるため、早めの判断が重要です。
騒音・異音の増加
通常の稼働音よりも明らかに大きな音や、「ガガガ」「キュルキュル」といった異音が聞こえる場合も注意が必要です。内部のモーターやギア、ローラー部分の劣化が進んでいると、このような音が発生しやすくなります。放置するとさらに大きなトラブルにつながりかねません。
異音が続く場合は修理やメンテナンスの対象ですが、部品供給が終了している場合や修理費用が高額になる場合には、買い替えを検討するのが現実的です。
修理コストの増加
複合機は消耗品交換や定期点検が欠かせませんが、修理のたびに数万円単位のコストがかかるようになると、買い替えたほうが長期的に経済的です。特にメーカー保証期間が終了すると、修理費用が高額化しやすいため注意が必要です。
部品供給終了のリスク
メーカーが部品の供給を終了すると、修理自体ができなくなるケースがあります。一般的に複合機の部品供給期間は発売から5~7年程度とされており、それを過ぎると代替パーツの確保も難しくなります。
部品が入手できない状態では不具合が起きても改善できないため、業務を止めないためにも早めの買い替え判断が必要です。
複合機の寿命を示すサインは、業務効率やコストに直結する重要な指標です。修理やメンテナンスで一時的に対応できる場合もありますが、頻発するようであれば本体の寿命と捉えるべきでしょう。
特に耐用年数を超えた機種では、修理費用の増大や部品供給の終了といったリスクも高まります。これらを踏まえ、長期的な視点で買い替えを検討することが、安定した業務運営につながります。
複合機の寿命を延ばす方法
複合機は高額な設備投資となるため、できるだけ長く使いたいと考える企業は多いでしょう。しかし、使用環境やメンテナンス方法によって寿命は大きく変わります。日々のちょっとした工夫で寿命を延ばせば、買い替えコストを削減し、業務効率の安定化にもつながります。
ここでは、複合機を長く使うための具体的なポイントを解説します。
日常メンテナンスを徹底する
複合機は精密機器であるため、ほこりやインク汚れが蓄積すると故障や寿命の短縮につながります。特に給紙ローラーや原稿台、操作パネルは汚れが発生しやすい部分です。
以下のように、定期的なメンテナンスを心がけましょう。
- 給紙ローラー:柔らかい布で回転させながら軽く拭き取る
- 原稿台(ガラス面):乾いた専用シートで清掃
- 操作パネル:OAクリーナーを含ませた布で拭く
クリーニングの際は、必ず電源を切ってから行い、具体的な清掃方法は取扱説明書に従うことが大切です。
設置環境を最適化する
複合機の寿命は設置環境によっても左右されます。直射日光や高温多湿、ほこりの多い場所に置くと、内部部品の劣化や紙詰まりの原因になります。
最適な温度・湿度の条件はメーカーごとに異なるため、必ず取扱説明書に記載された推奨環境を確認し、それに従って設置することが重要です。
純正トナーや適切な用紙を使用する
コスト削減のために非純正トナーや規格外の用紙を使用すると、印刷不良や部品故障のリスクが高まります。純正トナーやメーカー推奨の用紙を使うことで、印刷品質が安定し、内部部品の負担も軽減できます。
電源管理にスリープモードを活用する
主電源の頻繁なオン・オフは、基盤や内部パーツに負担を与え、故障を招きやすくなります。
複合機は長時間使用しない場合でも、主電源は切らず、スリープモードを活用するのが望ましい運用方法です。必要なときにすぐ使用でき、電力消費も抑えられます。
定期的に印刷して稼働させる
使用頻度が低すぎるのも問題です。長期間印刷を行わないとトナーが固まってしまい、印刷不良や部品交換の原因となります。
最低でも1週間に1回程度は印刷を行い、複合機を稼働状態に保つことが寿命を延ばすポイントです。
複合機を長く安心して使うには、日常的なメンテナンス、適切な設置環境、純正消耗品の使用、電源管理、定期的な稼働の5つが欠かせません。これらを意識することで、耐用年数を超えても安定して使える可能性が高まります。
日々のちょっとした工夫が、結果として大きなコスト削減や業務効率化につながるのです。
まとめ
複合機は、税務上の「法定耐用年数(5年)」と、実際の使用環境に左右される「物理的寿命(5~10年)」の2つの視点から考える必要があります。会計処理や減価償却のルールを理解することはもちろん、買い替えのサインを見逃さず、日常的なメンテナンスや適切な環境管理を徹底することで、寿命を大きく延ばすことができます。
修理コストの増加や部品供給終了といったリスクが高まる前に計画的に更新を検討することは、業務の安定とコスト削減の両立につながります。
「耐用年数=寿命」とは限らないからこそ、自社の利用状況に合わせて最適な判断を行うことが大切です。本記事で紹介したポイントを踏まえ、複合機を長く安心して使い続けられる運用を心がけましょう。